第5話 激動の幕開け <大正時代>
日露戦争は日本を大国へと変えた。これは、日本は他のあらゆる大国との軍事バランスを保たなければならなくなったと言うことである。
明治38年(1905年)には、アメリカのフィリピン支配と日本の朝鮮半島支配を相互に承認、また日英同盟の更新時には、日本の朝鮮半島支配を認めさせる代わりにイギリスとのインド防衛の義務を負うなど、諸大国と今までのような隷従関係ではなく、協調、対等な関係を持つようになった。
明治40年(1907年)には、フランスのインドシナ支配と日本の朝鮮半島支配を相互に確認。また、ロシアとは日露協商が成立、ロシアは、外モンゴルと北満州を、そして日本は南満州と朝鮮半島の支配権益を得ることで合意した。
このように、日本は諸大国に朝鮮半島支配を認められ、大陸進出の足がかりを得た。しかし、それは同時に、ハワイ、フィリピンと侵略を続け、太平洋の覇権を目指したアメリカにとって、日本は目障りな存在になった時でもあった。アメリカが日本を仮想敵国の一員に加えたのが、まさにこのときである。(対日本はオレンジプランと言われた。)しかし、大正元年(1911年)の辛亥革命以後、欧米の進出により、日本の大陸政策も行き詰まりを見せてきた。
ところが、日本に大陸進出の好機が訪れる。大正3年(1914年)に勃発した第一次大戦により、ヨーロッパ諸国は中国からの一時的後退を余儀なくされ、日本は日英同盟を名目に連合国の一員として参戦、山東半島と南洋群島のドイツ権益を手中に収め、さらに、大正4(1915)「対華二十一カ条要求」などで中国に対する支配を強めようとした。
しかし、大戦で疲弊したヨーロッパ諸国に代わって世界の指導者的立場になったアメリカは、大正10年(1921年)に日本、イギリス、フランス、イタリア、中国、オランダ、ポルトガル、ベルギー、アメリカの9カ国が参加したワシントン会議で九カ国条約を採択、日本は山東半島など、第一次大戦で得た権益の殆どを失うことになる。この会議ではまた海軍軍縮条約が結ばれるとともに、日英同盟も廃棄され、日本は列強とは独立した路線を進むことを余儀なくされることとなった。
国内に目を転じると、日清・日露戦争の頃から、大規模な軍備拡張政策が展開された。戦時非常特別税は日露戦後には恒久税とされ、さらに石油消費税など新たに間接税が増加、国民の負担は増大した。また、日露戦争は勝利に終わったものの、賠償金を得ることができなかったため、外国債の返済などが財政を圧迫、重税がやがて物価の高騰を招いた。
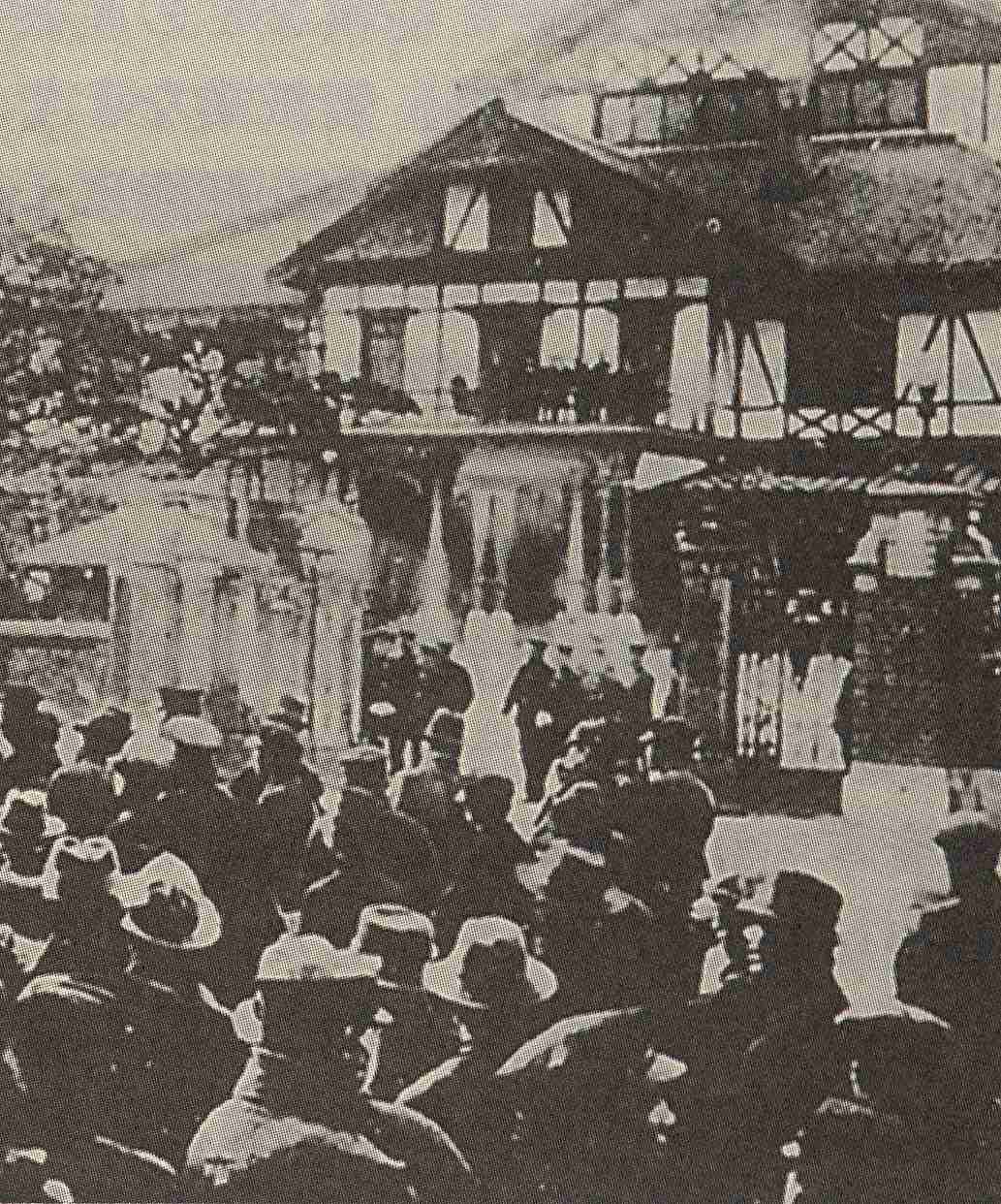 |
| 国会を取り囲む民衆 (「中学社会」大阪書籍より) |
こうした国民の負担の増加は民衆の不満を増大させ、明治38年(1905年)9月の日比谷焼討事件を頂点とする全国主要都市における日露講和反対運動を最初として都市民衆の暴動がしばしば発生した。また各地の商業会議所、実業組合に結集した中・小資本家も営業税など悪税反対運動を展開し、政府の軍備偏重の政策を批判した。またこの時期、都市部の知識人や中間層に自由主義の風潮が生まれ、普通選挙などを要求する運動が起こった。
このような民衆運動は、従来の官僚、軍部と政党の妥協による政治を否定、やがて広範な憲政擁護運動となり、ついには第三次桂内閣を打倒、山本権兵衛内閣を誕生させた。また、同内閣がシーメンス事件で倒れたのちは、元老をして民衆的人気のあった大隈重信を後継首相に推させるにいたった。
第一次大戦によって独占資本は巨大な利潤を得、多くの「成金」を輩出させたが、その一方で米価の急騰は国民生活を圧迫し、米騒動を引き起こした。米騒動はたちまち全国に波及し、ついに寺内軍部内閣を倒して、原敬政友会内閣を成立させるにいたった。
米騒動を境に国内政治は大きく転換し、労働者の組織は拡大し、労働運動が活発化し、大逆事件以来閉塞させられてきた社会主義運動や部落解放運動、学生運動、婦人運動など社会運動もおこり、大正11年(1922年)には日本共産党も結成された。
既成政党は、このように民衆の階級意識が益々強まる中、社会変革の危険を感じ、大正13年(1924年)の第二次護憲運動で清浦内閣を倒して成立した加藤高明の護憲三派内閣は、翌年、男子普通選挙法を治安維持法と抱合せにして成立させた。護憲三派内閣は、以後五・一五事件にいたるまでの政党政治の幕を開くものであった。
日清・日露両戦間に産業資本が確立した日本資本主義は、日露戦後には早くも独占段階へ移行し始めた。日露戦争後の鉄道国有化と南満州鉄道株式会社の設立をきっかけに企業熱が高まり、多くの企業の新設、拡張がおこなわれたが、明治40年(1907年)1月の恐慌で、投機的会社や中小銀行の倒産が相次いだ。その後、恐慌は鉄・紡績などの産業部門にも波及した。その結果、資本の集中が進み、精糖、肥料、製紙業などではカルテル化が進んだほか、三井、三菱などの財閥ではコンツェルン形態による独占の形成が進行した。
その一方で、日露戦争を多額の外債によって遂行した日本は、戦後の軍備拡張、植民地経営も外債に依存せざるを得ず、輸出の不振もあいまって輸入超過・正貨の減少を招き、破産寸前に追いやられた。
こうした経済状況で迎えた大正3年(1914年)の第一次大戦勃発はまさに「天佑」であった。開戦一年後には連合国からの軍需物資の注文が殺到し、欧米資本主義の商品市場であったアジア、アフリカ各地域からの商品注文も増加、輸出は空前の伸びを示した。
その結果大戦前には11億円の債務国であった日本は、大戦後の大正9年(1920年)には一転して28億円の債権国となった。輸出の好調に加えて輸入製品の杜絶は企業の新設、拡充をまねき、中でも重化学工業が目覚しい発展を遂げた。重化学工業の発展は設備投資を増大させ、そのために拡大した資金需要に応えるためにも銀行は合併、合同を推進した。その結果金融業における三井、三菱、住友、第一、安田の五大銀行の支配的地位が確立し、金融独占が他産業に先がけて大戦中に成立することになった。
好況は終戦後もしばらく続いたが、輸出の異常な増大を基礎とした好況だったこともあり、反動恐慌が起こった。大正9年3月の株式市場の暴落に始まった恐慌は、銀行169行の取付けで金融が混乱、やがて綿、木材、鉄鋼などほとんどの産業分野に及び、倒産、解散した企業は、同年318社、翌年には748社をかぞえた。この恐慌を通じて大企業への吸収合併が行われ、各分野で独占資本が確立した。政府、日銀は財界の要請に応じて3億6000万円にのぼる救済融資を行って恐慌を切り抜けたが、日本資本主義の脆弱な体質をそのままとしたため、以後の相次ぐ恐慌を招くこととなる。大正13年(1924年)の関東大震災による震災恐慌に対しても、政府は震災手形割引損失補償令を出して銀行救済を行ったが、この震災手形が結果的に昭和2年(1927年)の金融恐慌の直接的原因をなしたのである。
思想・文化面では、日露戦争の勝利は維新以来国民を縛り続けてきた国家的危機感から人々を解放し、西欧文明の外形的模倣に終始してきた明治文化のあり方に疑問をいだかせた。ここから個人の自覚または内面的充実をはかろうとする個人主義的傾向が生れ、この傾向は中等、高等教育の普及にともなって形成された都市中間層を中心に急速に広まった。
明治43年(1910年)創刊の雑誌『白樺』の同人、武者小路実篤、志賀直哉らは自己の個性に忠実であることが人類の意志にかなうことであるとして、その個人主義を人道主義、理想主義に結びつけて主張した。翌年女性解放を唱えて創刊した平塚らいてうらの『青踏』も、自我の拡充を基調とするものであった。こうした中で、政治の基軸に議会政治、政党内閣制を据えようとする法理論、政治理論が現れた。憲法学における美濃部達吉の天皇機関説であり、政治学における吉野作造の民本主義論である。美濃部の天皇機関説は、同僚で天皇主権主義の立場の上杉慎吉との大正元年から翌年の論争を通じて多くの支持を得、また吉野の民本主義も明治憲法の大権を政治原理の基礎とすることに反対し、近代憲法の根本精神「人民権利の保障、三権分立主義、民選議院制度」に基づく政治を主張した。ここから吉野は代議政治の改良とそのための言論の自由、普通選挙、他方において専制機構としての貴族院、枢密院の改革、統帥権独立の廃止などの議論を展開した。
しかしロシア革命と米騒動以後思想、文化の状況も大きく変化した。プロレタリア文化が生れ、既成のブルジョア文化に対峙する大きな力となった。大正10年(1921年)小牧近江らが創刊した『種蒔く人』はその出発点であり、それは大正13(1924)年に『文芸戦線』に引き継がれ、マルクス主義の影響も強めながら昭和初期には芸術の各分野に広がっていった。こうした中で民本主義も影響力を失い、大山郁夫のように社会主義に移行するものも生れてきた。大正12(1923)年白樺派の有島武郎は、未来の文化の銚い手は「第四階級」であることを肯定しつつ自ら命を断った。その4年後の昭和2(1927)年、芥川龍之介も「ぼんやりとした不安」を表明して自殺した。それは大正期の小市民文化の終焉を象徴していた。
大正期とくに第一次大戦後の文化におけるもう一つの特徴は資本主義の発展にともなうマスコミの著しい発達にあった。新聞、雑誌、映画、レコード、それに大正14(1925)年に放送を開始したラジオなどの媒体を通じて、大量の画一的文化が大衆に提供された。
このなかで今まで民本主義的論説をかかげて「大正デモクラシー」運動に大きな役割を果してきた新聞も、大量読者の獲得を目指す営利主義に転じた。マスコミによって流行歌、ベストセラー、映画スターなどが作り出され、大衆はこれを享楽し、消費していった。そして、マスコミによる通俗的な享楽主義は一面では、情報の大量伝達で人々の意識を混乱させていった。